
先日、FIFA(国際フットボール連盟)は、今年の11月に開催されるワールドカップ・カタール大会で、オフサイド判定を補助する半自動化システムを導入することを発表しました。
FIFAが主催大会でITを導入するのは今回が初ではありません。2014年のブラジル大会ではGLT(ゴールラインテクノロジー)、2018年のロシア大会ではVAR(ビデオアシスタントレフェリー)をそれぞれ導入しています。
なぜFIFAは、フットボールに続々とITを導入するのでしょうか。ITの導入は、本当にフットボールをより良いものにするのでしょうか。
そこで今回は、『ITはフットボールの魅力や価値を高めるのか』についてお話しします。
目次
5つの観点から見たITの存在
この問いに関しては、選手やチーム、観客や視聴者、審判、クラブ経営や試合運営、情報伝達という5つの観点から考えてみたいと思います。
選手やチームの観点
まずはじめに、選手やチームの観点でいうと、練習や試合でITを活用することで、選手やチームが今どういう状態にあるのか、問題はどこにあるのか、どうすればこの状況を打破できるのかを人の感覚や経験ではなく、具体的な数値や可視化された情報をもとに判断、評価できるようになったことで、選手やチームのパフォーマンスだけでなく、フットボールのクオリティも格段に向上しました。
観客や視聴者の観点
次に、観客や視聴者の観点でいうと、現代社会はスマホなどのITツールによって、いつでも、どこでも、誰でも、さまざまな情報を気軽に、手軽に入手したり活用できるようになりました。
たとえば、チケットの入手、会場までのアクセス、スタジアムの入場、売店でのオーダーや支払い、試合観戦しながら気になるシーンをスマホでチェックできるなど、ITによってフットボールの楽しみ方が多様化したり、利便性が高まったことで見る側の満足度は高まりました。
審判の観点
それから、審判の観点でいうと、かつては反則となる事実がはっきりと映像で確認できたとしても(たとえば、86年メキシコ大会の「神の手」ゴール)、現場の審判が自分の目で見たものが全てで、ITを判定のツールとして使うことは認められていませんでした。
これが近年、IFAB(国際フットボール評議会)がITの活用を認めたことで、誤審率は格段に減少(VAR導入試合では7%から1.1%)しましたし、審判にかかる負担も軽減しました。これによって、選手やチーム関係者、見る人、支える人が、よりフットボールを楽しめるようになりました。
クラブ運営や試合運営の観点
更には、クラブ経営や試合運営の観点でいうと、ITを活用したマーケティングを行うことで、より正確な情報やこれまでわからなかった情報が簡単に入手できるようになったり、ITを活用したサービスを行うことで、お客さんの満足度を更に向上させられるようになりました。
情報伝達の観点
最後に、情報伝達の観点でいうと、ITの進化によって映像の質が格段に向上したこと、いつでもどこでも誰でも見たい映像を見れるようにしたこと、更には、個人がSNSなどで簡単に発信できるようになりました。
以上のことから、ITはフットボールの魅力や価値を高めていると考えます。
ITによって審判のミスはなくなるのか
ただし、『ITによって審判のミスは完全になくなるのか』となれば、結論は変わってきます。
「ミス」に関しては以前にお話しましたが、準備に問題があったのか、情報収集に問題があったのか、情報処理に問題があったのか、意思決定に問題があったのか、対応に問題があったのか、能力に問題があったのか、環境や相手に問題があったのかなど、ミスにまつわる要因は多岐にわたります。
このうちITがサポートできるのは、情報収集から意思決定までの部分なので、判定後の対応や能力まではカバーできません。
また前提として、フットボールの試合で起きるさまざまな事象に対する最終決定は人間がすることになっているので、この前提が変わらない限りどんなに優れたITを導入したとしても、審判のミスが完全になくなることはないでしょう。
であれば、『情報収集から意思決定までをITが行えば、少なくとも判定ミスはなくなるのではないか』という考えもあると思います。それでも僕は、判定ミスはなくならないと思います。
3つの理由
その理由は主に3つあります。
①まず、フットボールの競技規則はファウルや不正行為に関する規定が事細かく示されていないので、何をもって反則とするのかが数値化しにくく、ミスが生まれる余地を完全に打ち消すことはできません。
②次に、競技規則には「主審は競技規則と『競技の精神』に基づいて判定を下すこと」と明記されているのですが、起きた事象が『競技の精神』に反しているのかが数値化しにくく、こちらもミスが生まれる余地を完全に打ち消すことはできません。
③それから、何が正解なのか、何をもって正しいとするのかは、その人の価値観や解釈の仕方、状況によっても違ってきますし、明確な線引ができないこともあります。
ですので、ITによって精度の高い判定が下されたとしても、その判定に納得いかない人たちは必ず存在しますし、その人たちからするとそれはミス以外のなにものでもないので、ミスがなくなるということはないと考えます。
ITによる正確な判定の是非
最後に、『ITによる正確な判定はフットボールを面白くするのか』について考えてみたいと思います。「正確な判定」をどう定義するかにもよりますが、ITを活用しようとしまいと、正確な判定はフットボールを面白くするとは限らないです。
なぜなら、たとえば、5cm 違う場所からフリーキック(FK)を始めた、10cm 違う場所からスローインを始めた、相手を軽く押した、邪魔した、シャツを掴んだとします。皆さんが試合中によく見かけるシーンです。
厳密に言うと、これらは全て競技規則に反していると言えるので、反則またはやり直しとなります。通常、FKは1試合30~40回ですが、上記のようなものを全て反則とすると、おそらく80~100回は試合が止まることになります。
FKやスローインも厳密に言えば正しく行われていないので、これらを加えると、少なくとも150回は試合が止まると推測します。
もしこれを本当に実行すると、選手も見る人も支える人も「いい加減にしてよ!」「いいよそれくらいは!」「もっとフットボールさせてよ!」と正確な判定に嫌気がさすと思います。
あるいは、VARのことを思い出してください。VARによって喜びや嬉しさが増えた反面、正確さを追求するあまり、かえってつまらなさやイライラが生み出されているのも、皆さんがよく知るところです。
まとめ
いかがでしたか。ITや正確な判定は、あくまで目的を実現させるための手段でしかありません。ではフットボールにおける目的とは何か。それは、フットボールを通じて多くの人が笑顔になったり、喜びを分かち合ったり、感動を共有してそれぞれの人生が豊かになることです。
そして、ITも人間も完全無欠ではなく、それぞれ強みと弱みがあります。ですので大事なことは、正確さと曖昧さのどちらかを切り捨てることではなく、人間の弱みをITが補完して、ITの弱みを人間が補完する関係を作ること、正確さを大切にしながらも曖昧さを楽しみ、柔軟さや寛容さを失わないことです。
それによってフットボールは、もっと多くの人に愛され、楽しまれるスポーツになっていくと思います。



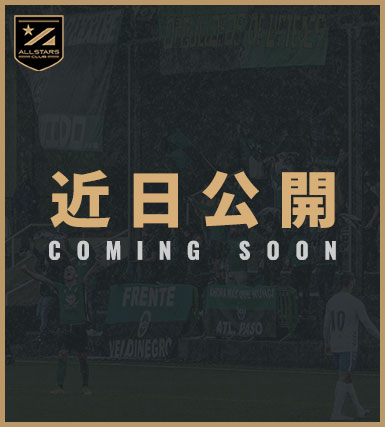
 TWITTER
TWITTER INSTAGRAM
INSTAGRAM FACEBOOK
FACEBOOK YOUTUBE
YOUTUBE































